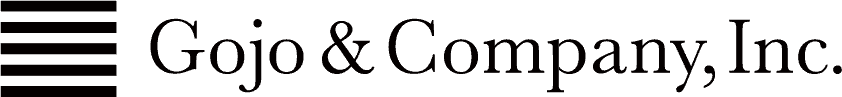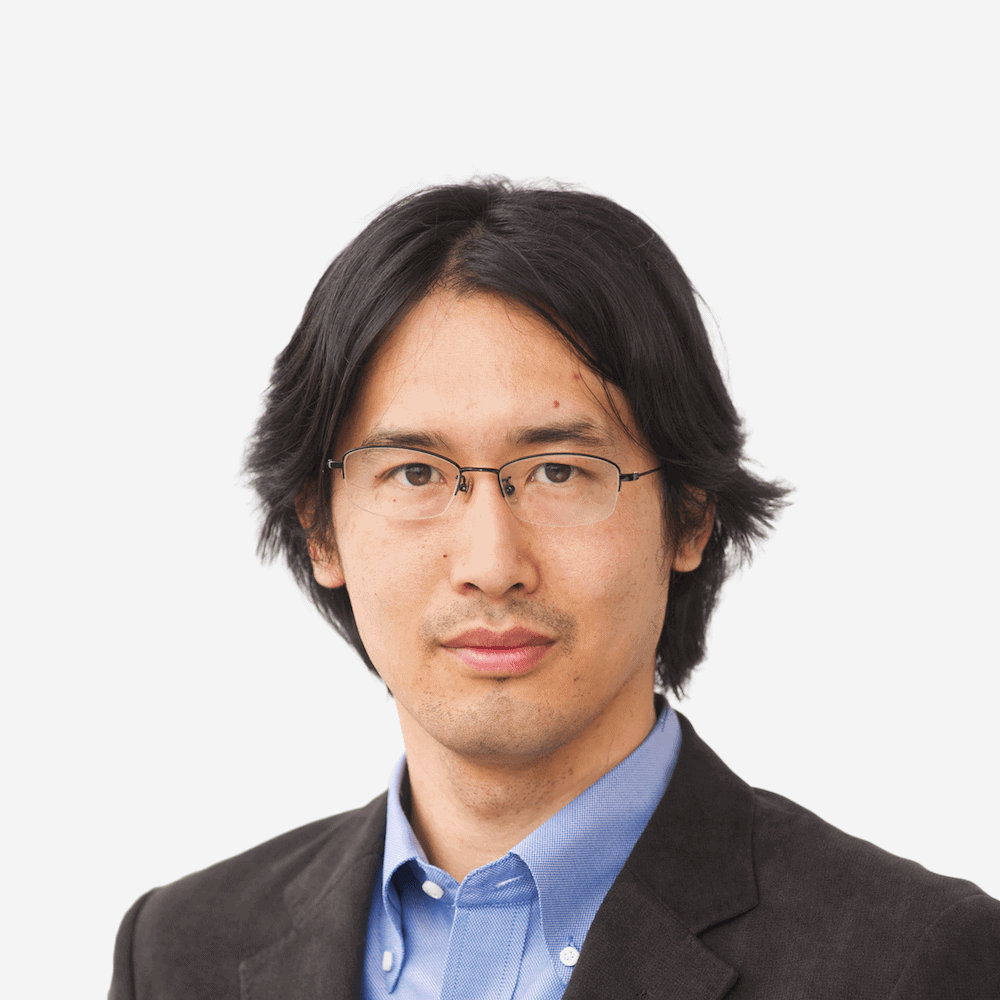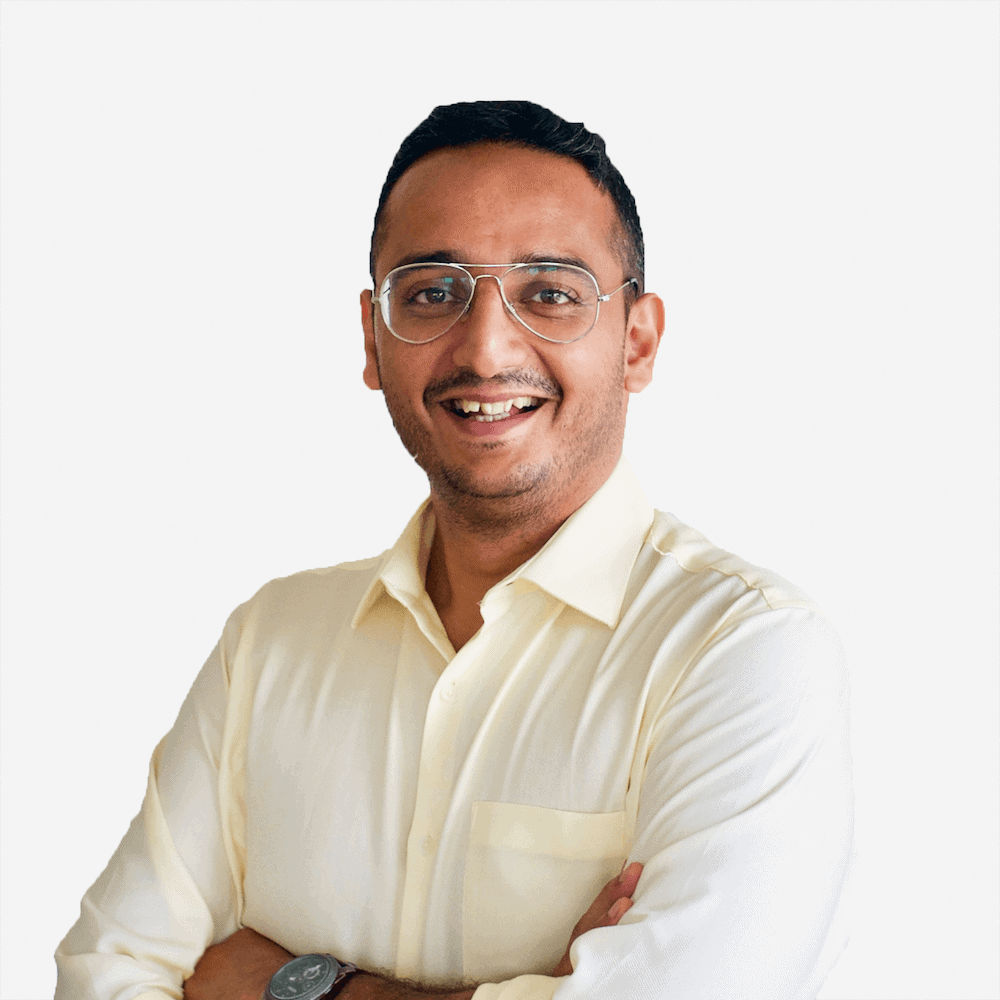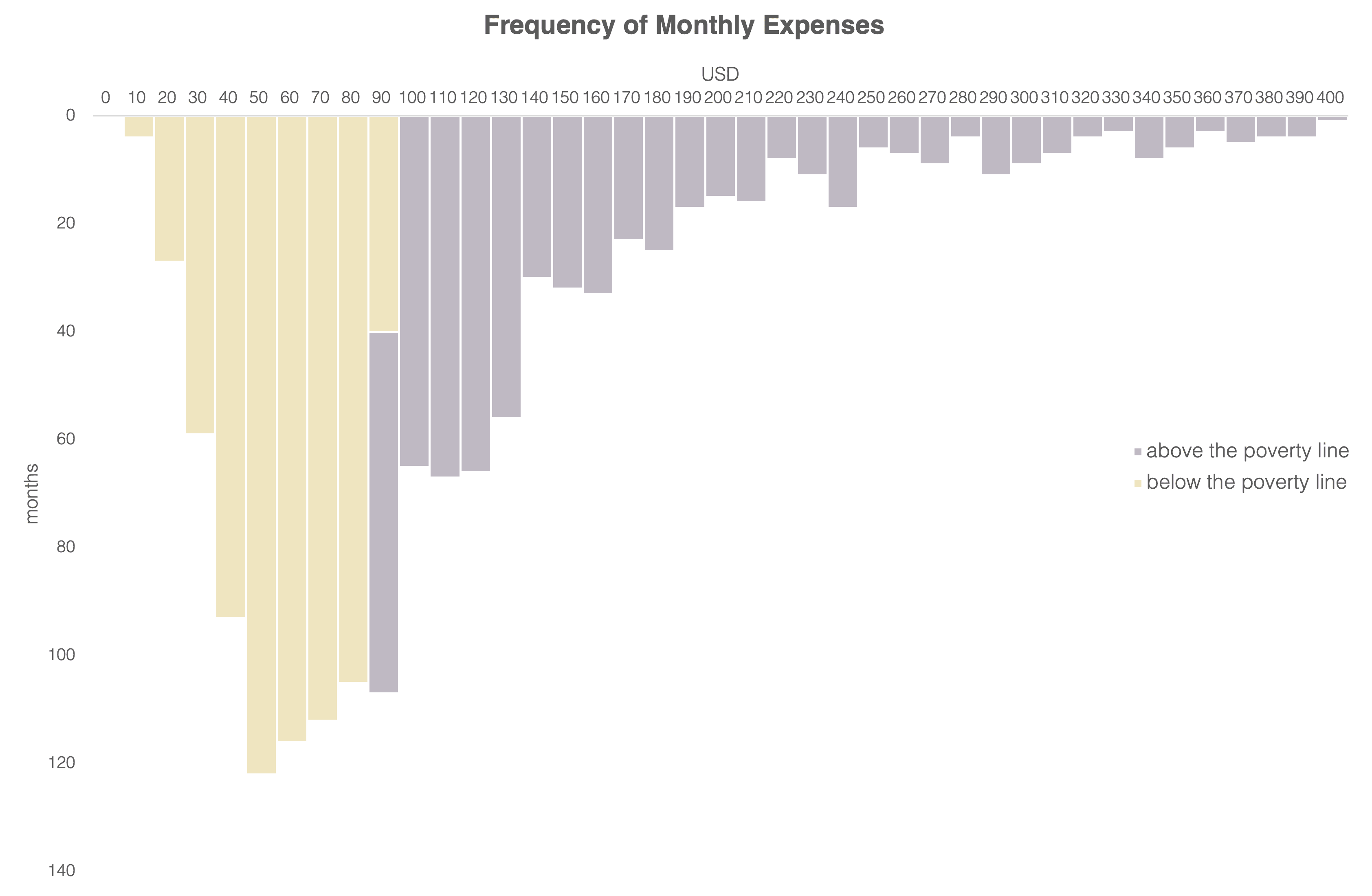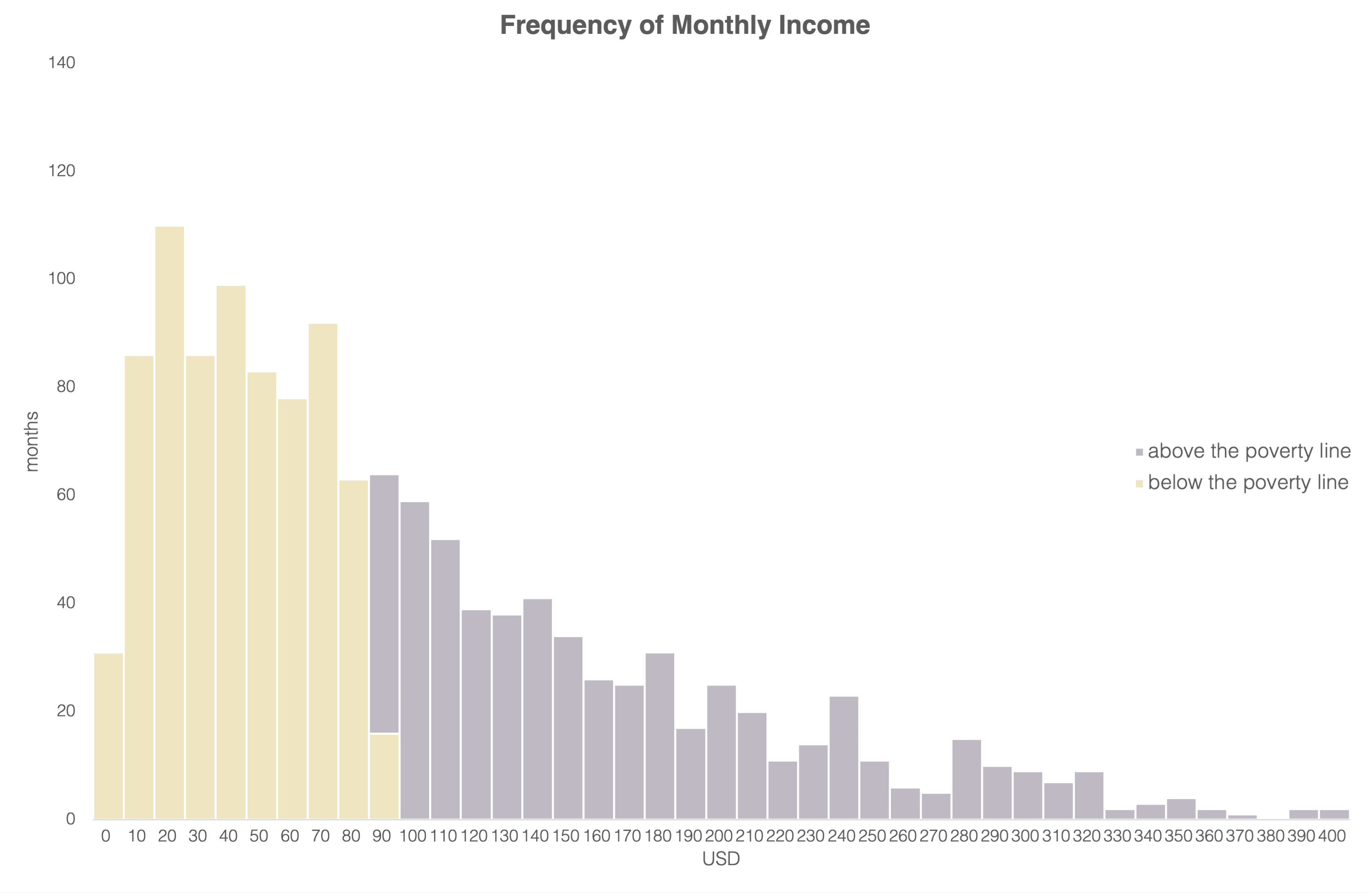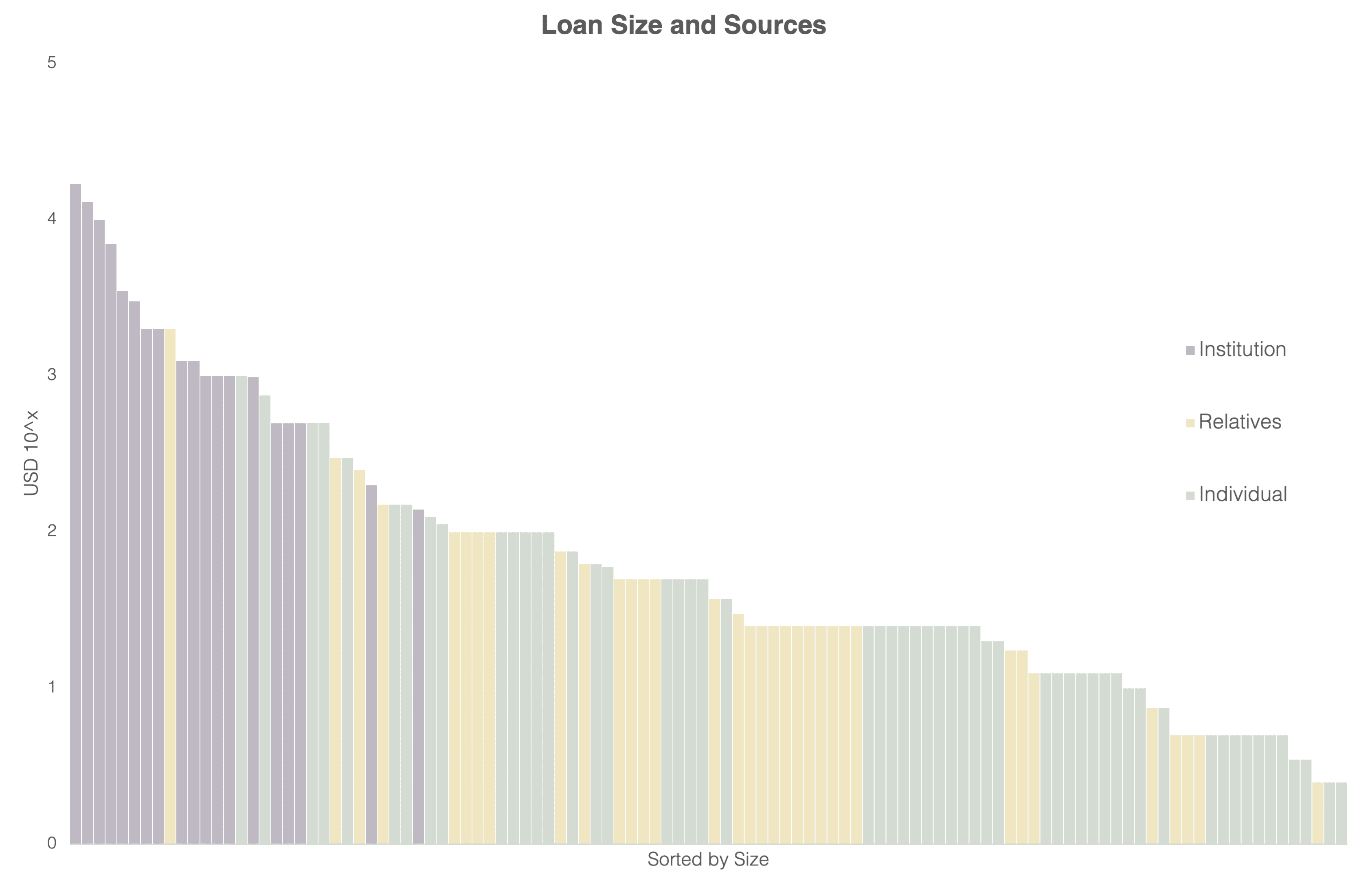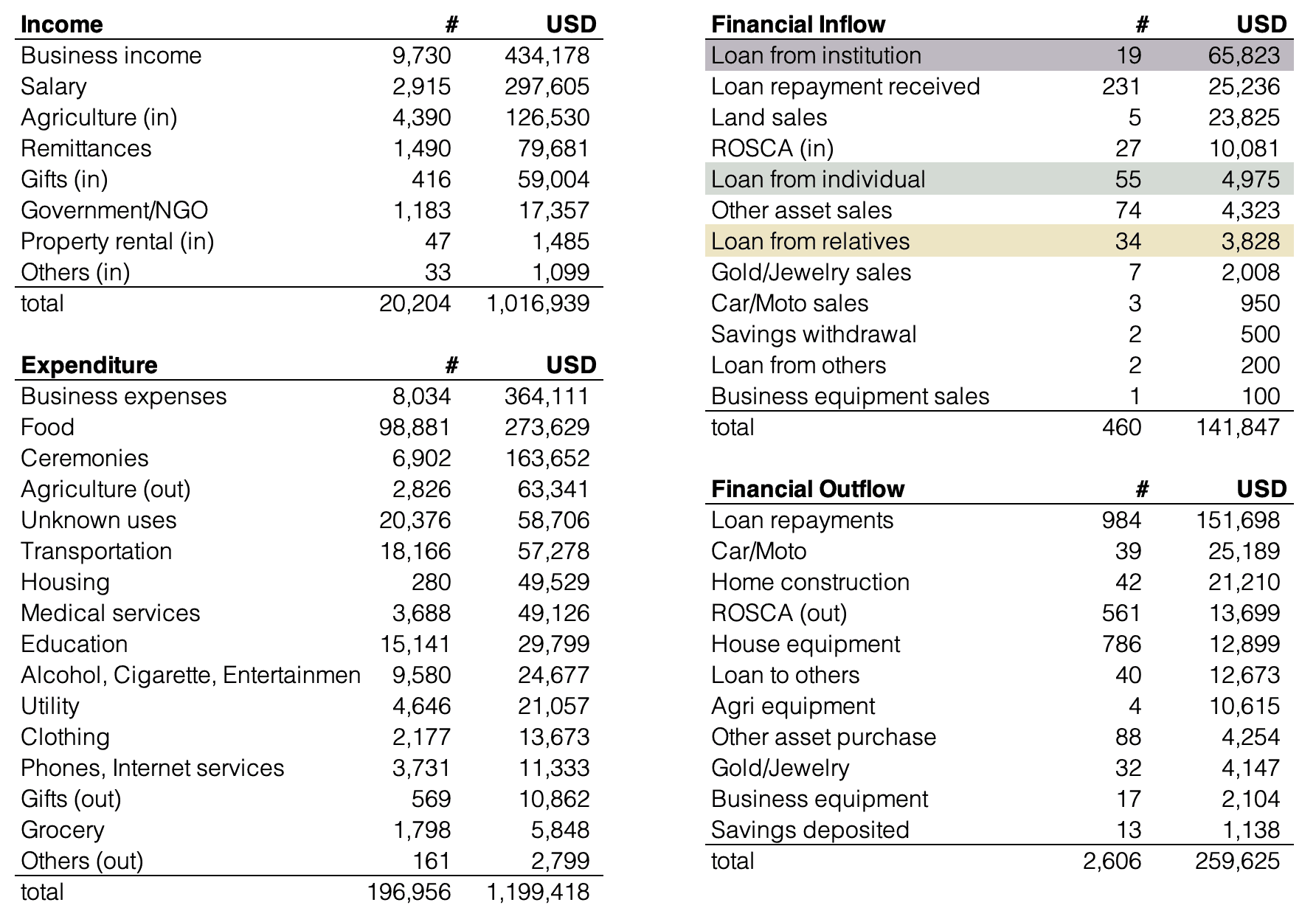現代の金融イノベーションの中でも特に興味深い存在であるマイクロファイナンスは「なぜ低所得層は銀行からお金を借りられないか」というシンプルながら切実な問いから生まれました。これまでは、少額の無担保融資はリスクが高く、手間もコストもかかるため、伝統的な商業銀行にとっては採算が合わないというのが常識でした。マイクロファイナンスはこのギャップを埋めるために生まれ、インドでは4つの大きなフェーズを経て発展してきました。
国家主導の補助金による融資(〜1990年代前)
独立後のインドでは、農村部の融資の約70%を高利貸し(マネーレンダー)が握り、銀行が担っていた割合は1%未満でした。これを変えるため、政府は1969年に大手銀行を国有化し、協同組合を推進、さらに1975年には地域農村銀行(Regional Rural Bank、RRB)を設立しました。その結果、1981年にはフォーマルな金融機関が農村部の融資の60%以上を担うまでに拡大しました。
しかし、この仕組みは1980年に始まった総合農村開発プログラム(Integrated Rural Development Programme、IRDP)のような、補助金付き融資に大きく依存していました。非常に低い金利と緩い返済規律のため、数百万件の貸し倒れが発生し、多くの借り手は融資を政府からの無償の給付金とみなすようになりました。1989年の債務免除がこれに拍車をかけ、銀行は「低所得層への融資は持続不可能」と結論づけました。この補助金依存モデルは行き詰まり、1990年代以降新たなアプローチがはじまりました。
自助グループの台頭(1990年代)
1990年代に、国家主導の補助金に頼った金融から持続可能性を重視したモデルへの大きな転換が起きました。その中で登場したのが自助グループ(Slef-Help Group、 SHG)モデルです。10〜20人ほどの女性たちが少額を貯金して互いに融資し合い、信頼関係と返済の規律を築きあげる仕組みです。これが広がったことで、グループに対してより大きな金額を貸し出すことが可能になりました。
この「社会的担保」によって、銀行が抱えていた担保不足と貸倒のリスクという二つの大きな課題への解決策が提示されました。1992年にNABARD(インド農業農村開発銀行)の支援で始まったSHG-銀行連携プログラムは高い返済率を誇り、1990年代後半には政府やNGOによって全国に広がり、インドの金融システムにおける重要な存在として認められるようになりました。
同時期に、マイクロファイナンス機関(Micro Finance Institute、MFI)も登場します。多くは非営利として低所得層に直接融資を行う組織で、効率的で返済規律のある融資が可能であることを示しました。これにより、「低所得層は銀行にとってリスクが高く融資を受けられない」という通説は覆されました。
マイクロファイナンスブームと危機(2000〜2011年)
2000年代はインドのマイクロファイナンスが爆発的に成長した時期でした。返済率の高さに注目した商業銀行がMFIへの資金供給を拡大し、多くのMFIが営利目的のノンバンク金融機関(Non-Banking Finance Company、NBFC)へと業態を転換していきました。その結果、プライベート・エクイティや国際市場から注目を集め、2005年には国連が「マイクロクレジット元年」を宣言しました。さらに2006年にはムハマド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞、そして2010年にはSKSマイクロファイナンスが株式市場に上場しました。
しかし、急速な成長には副作用もありました。MFIは成長を優先するあまり、本来最も重視すべき顧客との関係が軽視されるようになりました。同じ家庭が複数の機関から融資を受け過重債務に陥ったり、強引な取り立てが行われるケースも報告されました。これに歯止めをかけるため、2010年には最大の市場であったアンドーラ・プラデーシュ州で州政府がMFIに対して厳しい規制を導入し貸出を制限したため自転車操業に陥っていた顧客の返済率が急落し、マイクロファイナンス業界は大きな打撃を受けました。
この危機を受け、2011年にインド準備銀行(Reserve Bank of India、RBI)は新たにNBFC-MFIという業態を導入し、金利上限を設け、行き過ぎた貸出を防ぐための明確なルールを課しました。
ニューノーマル(2012年〜現在)
危機の後、多くのMFIが経営難に陥りました。2012年にはマイクロファイナンス機関法案が提出されましたが、成立することなく廃案となりました。それでもRBIの規制が一定の効果を発揮し、業界は徐々に再建されていきました。
同時に自助グループモデルも進化しました。2012年にNABARDが「SHG-2」を開始し、柔軟な返済が可能な融資商品の提供や融資を受けて成功した個人事業主がより大きなグループ融資(JLG, Joint Liability Group)へと移行してより多額の融資を受けることができる仕組みを導入しました。
最大の転機は2014年に訪れます。RBIがMFIに対し、商業銀行の代理販売を行うことを認めたのです。これによりMFIは単なる融資機関にとどまらず、銀行に代わって預金口座の開設、送金、保険、年金といった幅広いサービスを、銀行の代理人として提供できるようになり、大手銀行ではリーチできなかった低所得層にとっての「ラストマイル」の金融インフラを担う存在となりました。
今日、インドのマイクロファイナンスは少額融資にとどまりません。金融包摂を支える重要な柱として、何百万もの低所得世帯をより包括的な金融システムへとつなげる存在となっています。
今後の展望
インドにおけるマイクロファイナンスのあゆみは、決して平坦な道のりではありませんでした。国家主導の補助金を前提とした政策から始まり、草の根の自助グループ、そして商業化によるブームと危機を経て、現在のより規制が整った仕組みへと、常に進化を続けてきました。
しかし、変化し続けていてもその使命は一貫しています。社会的に弱い立場の人々の生活をより良くするための金融ツールを提供することです。テクノロジーの進歩や新しいモデルが生まれる中、マイクロファイナンスのあゆみはこれからも続きます。